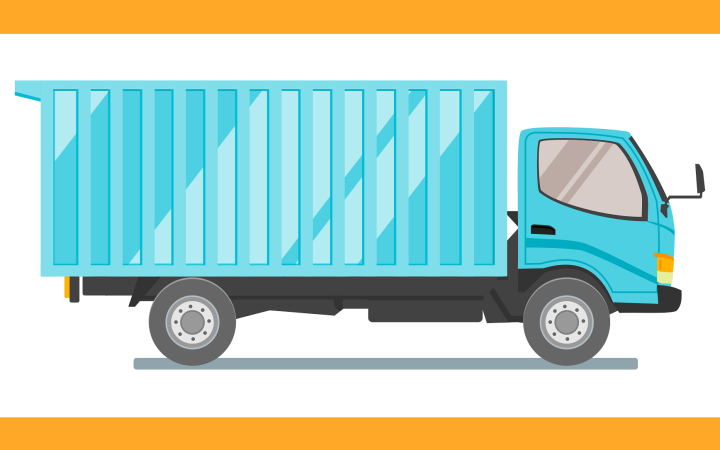【第3回】運送業の許可取得から営業開始までのリアルなスケジュールとは?
こんにちは。行政書士法人檀上事務所です。
連載ブログも第3回に入りました。前回は、一般貨物自動車運送事業の「5大要件」について解説しましたが、今回はそれらをクリアした上で、実際にどれくらいの時間で営業開始に至るのか?を、リアルなスケジュール感でお届けします。
「申請したらすぐ営業できる」と思っていませんか?
実は、許可が下りた後も“やるべき手続き”は山ほどあるのです。
全体の流れを把握しよう!許可取得〜開業までのロードマップ
まずは全体像をざっくり把握しましょう。
| フェーズ | 期間の目安 | 内容 |
|---|---|---|
| ① 事前相談・書類準備 | 約1〜2か月 | 営業所・車庫・車両・人員・資金の確保など |
| ② 許可申請 → 審査 | 約2〜3か月 | 地方運輸局での審査・役員法令試験など |
| ③ 許可通知 → 開業準備 | 約2か月 | 点呼体制・帳票整備・事業用自動車登録等 |
| ④ 営業開始 | 許可から約5か月後 | 開業届・営業開始報告・保険加入など |
つまり、ゼロからスタートする場合、最短でも5〜6か月はかかると考えてください。
許可取得後すぐに運送できない理由とは?
運輸支局から「許可証」が交付された瞬間がゴールではありません。
むしろ、そこからが“準備本番”です。
✅やるべきこと一覧:
- 事業用自動車の登録(緑ナンバー交付)
→ 陸運支局での手続き。書類不備があると遅延。 - 運行管理者・整備管理者の届け出
→ 所属・常勤の証明や承諾書が必要。 - 運送約款の備付・掲示
→ 標準約款を採用しても掲示義務があります。 - 点呼体制・日報・アルコールチェックの整備
→ 労働時間・運行安全記録などの「帳票づくり」が重要。
この段階で、「書類はあっても現場が整っていない」と営業開始報告が受理されません。
営業開始前の“監査”がある場合も
管轄運輸支局によっては、営業開始届を提出する前に**事前の実地確認やヒアリング(巡回指導)**が入ることもあります。
- 車庫の整備状況
- 日報・点呼簿の帳票類のサンプル
- 点呼実施体制の説明
- 事故対応マニュアルの整備状況
ここで不備があると、営業開始がさらに1〜2か月遅れるケースもあります。
つまり、「許可が出たらすぐ営業」というのは現実にはほぼ不可能です。
よくある“準備不足”による遅延とは?
行政書士として多数の現場を見てきた中で、許可後に営業開始が遅れる代表例を紹介します。
- 法人名義での預金残高証明が取れず再調整に
- 車庫の使用承諾が取れず別物件へ変更
- 運行管理者が退職してしまい代替探し
- 緑ナンバーの登録書類に不備があり手戻り
こうした“準備不足の地雷”を避けるには、事前相談の段階で全体設計をしておくことがカギです。
行政書士からのコメント:開業は“通過点”であり、継続運営のスタートでもある
私たち行政書士法人檀上事務所では、許可申請の代行だけでなく、許可取得後の営業開始準備・運行体制構築までワンストップで支援しています。
- 帳票類テンプレート提供(点呼簿・日報など)
- 開業後の巡回指導対策マニュアル作成
- 労務・安全管理に関する外部専門家連携
「許可が出たけど、動けない」――そんな状況を防ぐためにも、開業支援の“伴走型”支援をご活用ください。
👉次回予告:【第4回】事業計画書・資金計画書の作り方
– 運輸局も銀行も納得する“現実的かつ前向きな数字”の描き方とは?