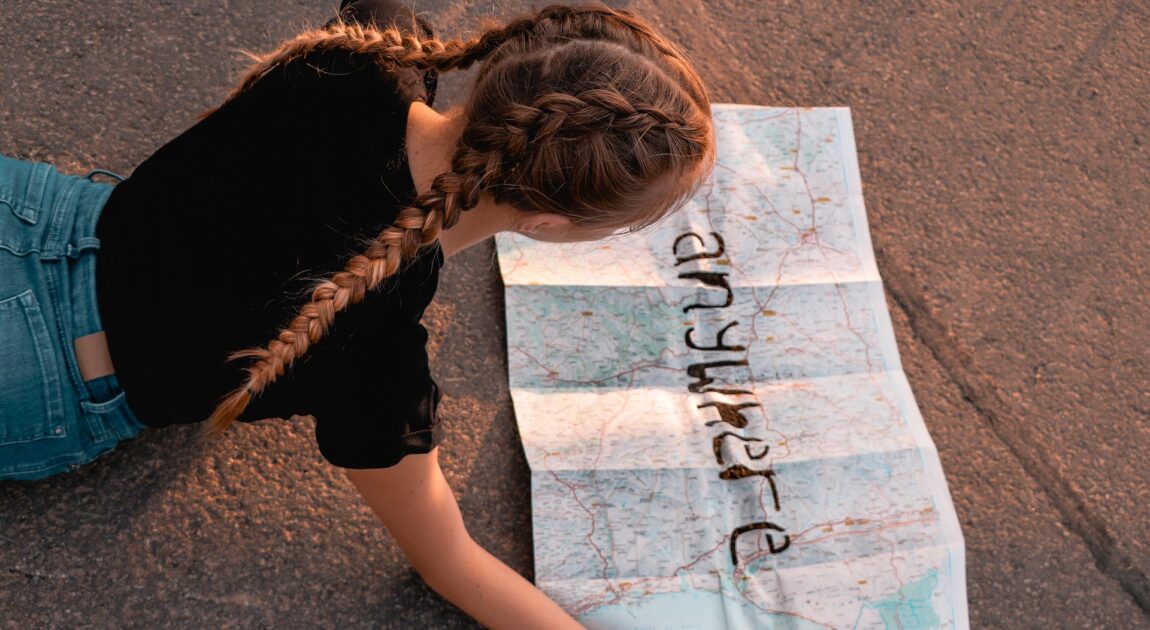風営法における周辺調査の実務 ― 立地規制・距離制限と申請書類の関係性
◆ 周辺調査の位置付け
風営法に基づく許可申請の成否を分ける最も重要な要素のひとつが「周辺調査」です。法律上、店舗自体の構造設備が基準を満たしていても、立地が不適合であれば一切営業が認められません。
風営法第4条は「営業所の周囲一定距離内における規制施設の存在」を定めており、これが各都道府県条例によって細かく補強されています。
◆ 規制の対象となる施設
代表的には以下が挙げられます:
- 学校(小・中・高・特別支援学校)
- 保育所、幼稚園
- 児童福祉施設(児童館、養護施設など)
- 病院、診療所
- 図書館、公園、その他の公益施設
ただし、条例により対象は拡張される場合があり、例えば「老人福祉センター」「公民館」「運動施設」などが含まれることもあります。
◆ 距離制限の基準
距離の測り方も重要です。
- 「敷地境界線から直線距離で100m」
- 「道路中心線を経由して200m」
といった具合に、自治体ごとに異なる基準が存在します。測定方法を誤ると、調査結果が不正確になり、後の申請で却下されるリスクがあります。
◆ 実務における調査プロセス
- 事前ヒアリング:依頼者から候補物件を提示してもらい、条例基準を確認。
- 地図調査:住宅地図・ゼンリン・GISを活用し、対象施設の有無を特定。
- 現地踏査:徒歩で周囲を確認し、対象施設の位置や看板を撮影。
- 距離測定:実測(巻尺)または測量アプリを併用。道路中心線経由の場合はルートを明示。
- 調査報告書:地図、写真、距離算定表を添付し、許可申請添付用に整備。
◆ 実務上の留意点
- 条例ごとの差異:隣接市町村でも規制内容が異なるため、必ず所轄警察署での確認が必要。
- 施設の解釈問題:「保育施設にあたるか否か」など、警察判断に委ねられる場合がある。
- 契約タイミング:物件契約後に不適合と判明すると、事業計画全体が破綻する恐れがある。
◆ 行政書士の役割
行政書士は、依頼者に対し次のサポートを行うことが期待されます。
- 物件選定段階からの助言
- 調査・測定の実施
- 書面による証拠化(報告書の添付)
- 所轄警察署への事前相談同行
これにより、依頼者が安心して投資判断できる環境を提供することができます。
◆ まとめ
周辺調査は、単なる付随手続きではなく「開業の可否を決定づける核心部分」です。条例・距離基準・測定方法を正しく理解し、的確な報告書を作成できるかどうかが、行政書士の実力を測るリトマス試験紙にもなります。